NHK「なぜ人間になれたのか」~そしてお金が生まれた~
昨日、2月26日のNHKスペシャル
「ヒューマン なぜ人間になれたのか 第4集 そしてお金が生まれた」
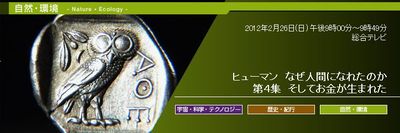
お金という概念が生まれて、人間の営みがどう変化したのを綴る50分だった。
昔は、今も地域によってはそうですけど、その日暮らしの不安定な生活でした。
そこで、狩猟での成果を持って帰ると、みんなで分配するのが当たり前の、
いわば横並びの社会でした。
そこで文明が生まれ、「麦」をお金にしてモノの交換がスムーズに行われ、
「職業」が生まれ、得意分野にそれぞれ特化して(比較優位の法則)、
総生産が増加し、人口も増えたということでした。
(この時すでに「ハープ弾き」という芸能を生業にしてた人が居たのに驚き。)
「人間は交換という行動ができる」というのが、ここの大きいキーワードになります。
人間に知能が近いチンパンジーで実験をしていました。
リンゴとブドウ、チンパンジーに好きな方を取らせると、
リンゴ20%・ブドウ80%という結果なのに対し、
あらかじめチンパンジーにリンゴを持たせておいて、
人間がブドウへの交換を求めると、応じたのは僅か2%でした。
チンパンジーは持ち逃げされても誰かに訴えることができず、
警戒して交換しないそうです。
これが何を表しているかと言うと、
人間のネットワークが、裏切りにくい社会を作り、
その中での信頼関係から生まれる、
「交換」が経済活動の始まりの由来ということ。
お金を手にし、さらに麦から銀・金属に変わると、
富の蓄財が可能になり、長期計画が立てられる安定した生活を目指すことになります。
分配が当たり前で、助け合いのために働く世の中から、
自分の富のために、自分で未来を切り開くために働く社会に変わりました。
でもそこには、
「この無条件分配のおかげで生活が保証されていた伝統を重んじる」か、
「その日暮らしではない、長期的な安定した人生設計のために必要な競争」との間で、
大きな葛藤があり、世界中のあらゆる町がその葛藤の末に、
発展と競争を選んだという歴史があります。
しかしまた別の実験では、
人間は自分が富を得る快感より、目の前の相手と富を分かち合う方が、
快感を得られると脳科学的に実証していました。
これはまだ人間の本質の中に「分かち合い」が確かにあるということで、なんか安心。
巻末に、番組では、
「人類は目の前の相手と分かち合うことはできるが、
地球の裏側や未来の人たちに対しても分かち合うことができるか」
ということを提起していた。
個人的に、発展と競争をコントロールすることが今を生きる我々のテーマなのではないか、と思う。
世界的に人口は増えていくが、日本の人口は減少している。
これは産業革命以降、一国の人口が減るという現象が歴史的にも初のケースで、
(戦争やジェノサイド等の一時的な減少は除く)
今の日本は、成熟期以降の経済モデルや人類全体の方向性、
新しい価値観の発生など、実験対象であり、歴史上大きな転換期らしい。
(仮に世界が日本と同じく人口が成熟していったとして)
そんな中、分かち合いという原点回帰をしたり、
消費を減らしたり、モノを共有していったり、自給自足で暮らすなどする、
今までの価値観だと退化だとさえ言われてしまう方向性が、
実は人類が生きながらえる方法なのかもしれない。
と考えた夜。
「ヒューマン なぜ人間になれたのか 第4集 そしてお金が生まれた」
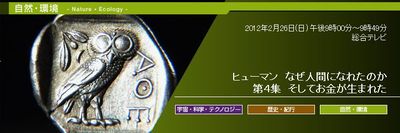
お金という概念が生まれて、人間の営みがどう変化したのを綴る50分だった。
昔は、今も地域によってはそうですけど、その日暮らしの不安定な生活でした。
そこで、狩猟での成果を持って帰ると、みんなで分配するのが当たり前の、
いわば横並びの社会でした。
そこで文明が生まれ、「麦」をお金にしてモノの交換がスムーズに行われ、
「職業」が生まれ、得意分野にそれぞれ特化して(比較優位の法則)、
総生産が増加し、人口も増えたということでした。
(この時すでに「ハープ弾き」という芸能を生業にしてた人が居たのに驚き。)
「人間は交換という行動ができる」というのが、ここの大きいキーワードになります。
人間に知能が近いチンパンジーで実験をしていました。
リンゴとブドウ、チンパンジーに好きな方を取らせると、
リンゴ20%・ブドウ80%という結果なのに対し、
あらかじめチンパンジーにリンゴを持たせておいて、
人間がブドウへの交換を求めると、応じたのは僅か2%でした。
チンパンジーは持ち逃げされても誰かに訴えることができず、
警戒して交換しないそうです。
これが何を表しているかと言うと、
人間のネットワークが、裏切りにくい社会を作り、
その中での信頼関係から生まれる、
「交換」が経済活動の始まりの由来ということ。
お金を手にし、さらに麦から銀・金属に変わると、
富の蓄財が可能になり、長期計画が立てられる安定した生活を目指すことになります。
分配が当たり前で、助け合いのために働く世の中から、
自分の富のために、自分で未来を切り開くために働く社会に変わりました。
でもそこには、
「この無条件分配のおかげで生活が保証されていた伝統を重んじる」か、
「その日暮らしではない、長期的な安定した人生設計のために必要な競争」との間で、
大きな葛藤があり、世界中のあらゆる町がその葛藤の末に、
発展と競争を選んだという歴史があります。
しかしまた別の実験では、
人間は自分が富を得る快感より、目の前の相手と富を分かち合う方が、
快感を得られると脳科学的に実証していました。
これはまだ人間の本質の中に「分かち合い」が確かにあるということで、なんか安心。
巻末に、番組では、
「人類は目の前の相手と分かち合うことはできるが、
地球の裏側や未来の人たちに対しても分かち合うことができるか」
ということを提起していた。
個人的に、発展と競争をコントロールすることが今を生きる我々のテーマなのではないか、と思う。
世界的に人口は増えていくが、日本の人口は減少している。
これは産業革命以降、一国の人口が減るという現象が歴史的にも初のケースで、
(戦争やジェノサイド等の一時的な減少は除く)
今の日本は、成熟期以降の経済モデルや人類全体の方向性、
新しい価値観の発生など、実験対象であり、歴史上大きな転換期らしい。
(仮に世界が日本と同じく人口が成熟していったとして)
そんな中、分かち合いという原点回帰をしたり、
消費を減らしたり、モノを共有していったり、自給自足で暮らすなどする、
今までの価値観だと退化だとさえ言われてしまう方向性が、
実は人類が生きながらえる方法なのかもしれない。
と考えた夜。







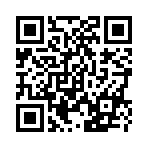


書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。